 もとにもどる
もとにもどる
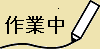
明治政府の外交責任者(外交事務総督)である東久世も伊達も「神戸での衝突に対する日本側の意見」を主張した気配はない。
東久世は外国公使団に天皇の国書を渡し、新政府の成立と外交権が自分たちにあることを宣言することが役目上の目的だったとしか思えない。
伊達は、岡山藩に発砲号令之者の人定(氏名など)を提出させ、それを外国側に報告した。そして、謝罪文を配布している。同じく彼の役目は、岡山藩に「発砲号令之者」を指し出させることであった。(その者を切腹させることについては、助命との関係も見る必要があるが、資料を見る範囲では積極的に動いたように思えない)。
この時の日本外交団の仕事は、外国側と交渉するというより、外国公使団をなだめて説得することであった、と考えざるを得ない。それしかない状況だったとも言えるが、もう少し何とかならなかったのかな、と個人的には思う。
その後の歴史を考えても、西欧に文句を言わないのが、日本外交の特徴の一つであるかも知れない。(その分、アジアには根拠のない優越感を持っていたりするが)
指揮を執った二人に共通しているのは、西洋文明に対する強い崇拝である。東久世も伊達もイギリス軍艦オーシャンを見学するなど、外国の文物(おそらく特に兵器)に非常な関心を持っている。これは、パークスなどしたたかな外交官にうまく誘導された気配がある。
武器だけでなく、社会制度についても同じように畏敬の念を持っていたのではないか。その一つが「万国公法」である。
東久世は「田舎の兵士ども各国交際の道を知らず日本の武家の法のみ心得て右様の不始末をなしたるは甚だ恥入るところである」と外国公使に言い(東久世の回顧録『維新前後 : 竹亭回顧録』頁246)、伊達は、イギリス外交官たちと飲食を共にし、書籍をもらい、パークスに「万国公法は天法である」と言っている(『伊達宗城公御日記』頁37)。
これら西洋文化に対する畏敬と劣等感は現代の日本社会にも底流としてあるような気がする。今でも、外国の制度や文化を自国を評価する軸にすることは多い(そしてそれは「西欧に比べて日本は・・・」という文脈による日本批判が多い。)
世界共通の何か、理想に近い何かがこ西欧にあると考え、宇内之公法にそれを見たのかも知れない。
アジア・太平洋戦争で負けたから西洋コンプレックスが生まれたという感覚でいたが、そうではなく、西洋に対する崇拝とコンプレックスは明治初頭から一部支配層では強くあったと思うようになった。先の戦争の敗北でより強くなった可能性もあるが、この辺は別途検討が必要である。
伊達は瀧の助命に対し、どう考え、どう動いたか。資料を読む範囲では結局分からなかった。
五代の発言の前に伊達の指示があったのではないかと、『御留日記』『伊達宗城公御日記』及び池田家文庫中の『兵庫一件始末書上』以下の資料を読んでみたが、それらしい記述はなかった。むしろ、五代を諫めたり(『伊達宗城公御日記』頁38)、(瀧を助命したあとで、備前藩が逆らったら)迷惑である、さらに東久世の落ち度になるので宜しくないと思ったととれる記述がある(同頁30)。
一方、岡山藩留守居・澤井権次郎などに処断(瀧の切腹)を実行に移すことを知らせた際に落涙し、助命交渉の不調を聞き「残念千万也、初発之応接ナラとふか助ケラレタラン可惜(以下略)」と記し(同41)切腹の報を聞いて、和歌を作っている(『御留日記』頁46)。
伊達自身は最初から「宇内之公法」による処断を決めており、一月二十日の廟堂の会議でもその方針で会をまとめた(『復古記』巻二十三、明治元年正月二十日。頁666)。この事実と彼の「初発之応接ナラとふか助ケラレタラン」という感慨は矛盾するような気がする。
本来は優しい人で、しかし国家存亡の時なので心を鬼にして、という評価もあるかも知れないが、サイト管理人にはそう感じられない。代々平民の管理人には、公家とか大名の感覚は理解できないのかとも思う。
明治[新]政府と言い、宇内之公法と言いながら、事件の解決法は、幕府権力が強力な時代の藩のやり方を踏襲している。理不尽であっても反抗せず、藩内の誰かに詰め腹を切らせて藩を守る。御一新でも何でもない気がする。
余談だが、現代でも疑獄事件などで現場の担当職員が自殺して、ことが収まり「トカゲの尻尾切り」と言われることがある。似ているようで、似ていないように感じる。
幕末にあちこちで、藩のために詰め腹を切らされる者がいたが、彼らは比較的藩の上位(ただし、トップではない)の者が多い。上位でなかった瀧の場合は、その後遺族がそれなりに遇されている。しかし、尻尾切りされた下位者の遺族が厚遇される例はあまり聞かない。
似ている点は、上層部のその後の栄達にほとんど影響がないことである。
岡山藩主池田家は茂政の後継者・章政が伯爵、西宮警衛隊の総督・池田伊勢(政和)は男爵、日置帯刀の養嗣子・忠信(健太郎)が男爵、東久世通禧と伊達宗城は伯爵、伊達の息子宗徳が侯爵などなど枚挙にいとまがない。
明治維新の側面の一つが見えてくる。
天皇のお気持ちを乱すべきでない、朝廷が裁断された、神戸事件ではこの言葉は何度か出てくる。しかし、『復古記』などを読むと、この決断に明治の天皇が中心的な役割を果たされていないことは明白である。
幕末の勤皇の志士のほとんどは天皇に会ったことがないはずである。しかし彼らは尊王を旗印に非合法活動を続け、権力機構の頂点にいる徳川幕府を倒し、錦旗を立てて、旧幕府に連なる兵力を朝敵とした。
この動きは「昭和維新」を標榜した若手軍人の動きと似ている。天皇の権威を背景に超法規的に何かを行おうとするのは、幕末の志士に始まった流れなのかも知れない。
神戸事件の資料を読みながら、瀧善三郎は英雄だろうか?と考えた。個人的には彼は英雄である。自分が死ぬことで、日置家や岡山藩、さらに新政府の窮地を救った。その上、彼の死には美学がある。立派に切腹をすることで、外国人を驚かせ、記録に残った。
しかし、彼が自身で切り開いた運命の結果招きよせた死であったかというとそうでないように思う。彼のように「強いられた行為の結果、英雄となった者」(以下「強いられた英雄」とする)で、すぐに思い浮かぶのが「特攻隊」の若者である。
彼らは残念ながら自分が死ぬことで国家を救うことはできなかった。しかも、彼らはある時から「英雄」でもなくなった。
しかし、彼らは彼らなりに与えられた境遇のなかでそれこそ「必死」で奮闘した。
滝善三郎は、昭和になって一時、英雄として称えられたようである。神戸永福寺での記念碑建立が昭和八年三月、朝日新聞の天声人語が「支那大陸での今次の戦次」を引き合いに攘夷を実行した者として瀧を称賛したのが昭和十三年三月、岡久渭城が『明治維新神戸事件』を上梓したのが昭和十三年六月、同じ六月、神戸大丸で「瀧善三郎正信を中心とする神戸事件回顧展」が開催された。瀧の生誕地であり、日置家の陣屋があった金川(現岡山市北区)で顕彰碑が序幕されたのが昭和十五年十一月である。
この動きには、対英米戦争へ向かう国情を背景にしたと思われる。強いられた英雄が称賛されるときは、気をつけた方が良いかも知れない。