西宮警衛 日置隊の編成(検討)- ⅳ -【調査途中  】
】
「吉備温故秘録 巻之八七 軍役」では、船印として釘抜の紋が多く使われている(『吉備群書集成 (十)』口絵、頁三―十二)。また、『法令 御定書追加』(慶応二年。池田家文庫、資料番号H2―21)に提灯に釘抜を中赤く描くようにある。
提灯の図と岡山藩の釘貫紋の図である。

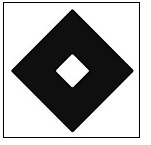
『レンズが撮らえた幕末維新の志士たち』に掲載されている天城池田家中老の布施五郎が東征の帰途に撮った写真の筒袖左腕にこの釘貫の相印が見える(頁五七)。
前記の法令などで定められていること、特に所属や階級の異なる二者が同じ相印をつけていることなどから、日置隊を含めた西宮警衛がこの釘抜の合印をつけていたのではないか、と推測している。そのことを直接記した資料を見ていないので、今後の調査でより明確にしたい。
【補足】
 布施藤五郎は同書によると銃隊(身分はデジタル岡山大百科によった)。「明治元年東征の帰途」撮影した写真の服装は、筒袖の上着の下にズボンをはき、腰に小刀をさしている。大刀は手に持っている。(頁五七)
布施藤五郎は同書によると銃隊(身分はデジタル岡山大百科によった)。「明治元年東征の帰途」撮影した写真の服装は、筒袖の上着の下にズボンをはき、腰に小刀をさしている。大刀は手に持っている。(頁五七)
 陣笠
陣笠
「調練足並略図」や「東都高輪風景」(『企画展示 行列にみる近世-武士と異国と祭礼と-』(国立歴史民俗博物館編、歴史民俗博物館振興会、二〇一二。頁一七二―一七三)を見ると、行軍の兵士は陣笠をかぶっている。
長州征伐行列図(第一次のようである。文化遺産オンライン)
『法令 御定書追加』(慶応二年。池田家文庫、資料番号H2―21)を参照すると、陣笠に日の丸をつけるように指示されている。

日置隊でも行軍中に陣笠をかぶっていたのではないかと推測するが、これについて資料は未見である。
これらの推測を組み合すと、小銃隊と大砲隊については、なんとなく服装と装備が見えてくる。調査して、もう少し具体的にしたい。
【参考資料】
- 『軍役之定』(池田家文庫、資料番号H2―36
- 「慶応四年侍帳」
- 岡山県史 第九巻
- 『岡山県の歴史』
- 『瀧善三郎神戸事件日置氏家記ノ写 同人遺書並辞世ノ歌』
- 『御津町史』
【銃に関する参考資料】『図説 幕末・維新の銃砲大全』『武具と防具 幕末編』およびインターネットサイト「幕末の銃器」を参照(確認令和元年五月一七日)。
 もとにもどる
もとにもどる