慶応四年神戸事件を考える
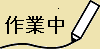
Ⅰ.争乱の時代
強引なアメリカ軍艦四隻が浦賀沖に姿を見せてから、時代は開国に向かう。それが政治的暗闘を招き、時に利用され、二百五十年続いた徳川幕府の権勢が揺らぎ、崩壊する。神戸事件は、その結末の内戦のはじめに起きた。
争乱の十五年を事件との関わりの視点でざっと見る。
1.ペリー来航から慶応元年まで
経済活動の拡大を目的とした欧米諸国による開国要求に対し、幕府はやむなく開国していく。攘夷を主張し、幕府の政治権力の正当性を否定する尊攘勢力。それぞれの勢力が政治的支配権をめぐって激しく争い続ける。
嘉永六年(1853)
●アメリカ東インド艦隊司令長官ペリー(M.C.Perry)浦賀港に来航、久里浜に上陸。
旗艦サスケノハナ号(蒸気軍艦、2450トン。『幕末外交と開国』頁12)とミシシッピー号、帆船サラトガ号とプリマス号の計四隻で浦賀港に来航、碇泊する。ペリーはアメリカ大統領フィルモアからの親書を携えていた。
これより先に通商を求めていたロシア艦船は幕府の指示に従い長崎に向かっていたが、アメリカ艦隊は、東京湾の入り口浦賀に停泊、ペリーは久里浜に上陸した。
【ペリー提督神奈川上陸図】

(この絵は、二度目に来航した時のもの。作者:ウイリアム・ハイネ原画 東京国立博物館デジタルコンテンツより引用。同館画像番号C0076965。東京国立博物館 研究情報アーカイブズ (2019/12/12確認)
(2019/12/12確認)
- ◎十二代将軍徳川家慶逝去。
- ◎十三代将軍徳川家定就任。
- ◇岡山藩房総警備を命ぜられる。
安政元年(1854)
- ◇岡山藩、安政の札潰れ。財政危機のため準備金が不足した岡山藩は藩札の十匁札を一匁札とした。このころ岡山藩の鴻池からの借銀24,677貫目に達していた。(『岡山藩』頁253)
▼管見1
幕末の諸藩の歴史を調べると、いくつかの藩で共通点が見いだされる。
- ①どの藩もただでさえ財政が逼迫していた上に、海防警備や兵制改革などによってそれに拍車がかかっている。
- ②藩内で尊王派と佐幕派が争う例が多い。さらに、反対派を暗殺したり、権力を握った方が敵対勢力を断罪したりすることもあった。
- ③この後、討幕の過程で顕著になるのが江戸にいる藩主と国方の家老たちの意識が異なることがある。基本的に江戸生まれ、江戸育ちの藩主は自領との結びつきが薄く、むしろ幕府との来歴や恩義を重視する傾向にあった。在国の家老は自領との結びつきが比較的強く、藩(国)の存続を第一に考える傾向があった。
-
- 岡山藩でも、財政の逼迫状況ははなはだしく、上記の安政元年(1854)の藩札の切り上げを強行せざるを得なかった。
- 尊王派と佐幕派の争いはあったが、『岡山藩』などの資料を見る限り、血で血を洗うようなことにはなっていないようだ。文久三年(1863)に藩主となった茂政の指揮のもと、兄徳川慶喜が将軍となり朝廷との関係が悪化する慶応三年末までは、尊攘翼覇が藩是であったようである。
▲たたむ
1856年
- ※アロー号戦争起きる。:アロー号事件とも呼ばれる。神戸事件の主要な関係者の一人、英国公使パークスは、この時広東領事代理として、関係している。(『パークス伝』頁363)。
安政五年(1858)
- ◎安政の大獄始まる。
 幕府、米・蘭・露・英・仏の五ヵ国と修好通商条約を締結する。:孝明天皇は日米修好通商条約の調印を拒否。このため、これらの条約は勅許を得ることなく締結された。安政の五ヵ国条約とよばれる一群の条約により「下田・箱館・長崎・新潟・兵庫の開港、江戸・大坂を開市し、それぞれに駐在領事を置くこと、開港場に外国人の遊歩規定を設けること、(以下略)」が約束された。
幕府、米・蘭・露・英・仏の五ヵ国と修好通商条約を締結する。:孝明天皇は日米修好通商条約の調印を拒否。このため、これらの条約は勅許を得ることなく締結された。安政の五ヵ国条約とよばれる一群の条約により「下田・箱館・長崎・新潟・兵庫の開港、江戸・大坂を開市し、それぞれに駐在領事を置くこと、開港場に外国人の遊歩規定を設けること、(以下略)」が約束された。
▼管見2
後に、「不平等条約」という評価が定着していくが、阿片戦争についてはもちろんアロー号戦争の情報を得ていた幕府は、欧米諸国の軍事力が強大であることを知っていたため、仕方なく妥協したという見方もある。
交渉の過程についても『現代語訳 墨夷応接録』のように評価するものもある(頁11―12)。朝廷勢力が実権を握った後に攘夷を行わず、開国したことを見れば、幕府の弱腰が必ずしもまちがっていたとは思えない。暴勇で国を亡ぼすのは為政者のとる道ではない。また、破壊活動を行う攘夷派の存在がなければ、もう少しうまく交渉できた可能性もある。
▲たたむ
※この後、ポルトガル・ベルギー・デンマーク等と修好通商条約を締結するが、これ以降の外交事案は衝突時に関係した六ヵ国(アメリカ・イギリス・フランス・オランダ・プロイセン・イタリア)のみを抜粋する。また、条約名もいくつか異同があるが、一般的に用いられる「修好通商条約」で統一する。
【参考】
幕末の開国条約一覧
安政六年(1859)
- 〇八十八卿の列参奏上。日米修好通商条約に反対する公卿が抗議する事件。明治天皇の外祖父中山忠能(明治政府で議定)、長谷信篤(同前)、岩倉具視など八十八人の堂上貴族が反対の座り込みをした。
安政七年/万延元年(1860)
- ◎桜田門外の変起きる。井伊直弼謀殺される。安政の大獄終焉。
- ※北京条約締結。アロー号戦争終結。これにより天津が開港され、九龍半島をイギリスに割譲。
 幕府、プロイセンと日普修好通商条約を締結。
幕府、プロイセンと日普修好通商条約を締結。
1861年
文久二年(1862)
 幕府の文久遣欧使節団、江戸・大坂の開市、兵庫・新潟の開港を五ヶ年延期するロンドン覚書を調印。同使節団は最終的にイギリス・オランダ・プロイセン・フランス・ポルトガルと同様の覚書を交わす。
幕府の文久遣欧使節団、江戸・大坂の開市、兵庫・新潟の開港を五ヶ年延期するロンドン覚書を調印。同使節団は最終的にイギリス・オランダ・プロイセン・フランス・ポルトガルと同様の覚書を交わす。 生麦事件起きる。薩摩藩国父・島津久光の行列に、騎乗のイギリス人四人が乗り入れる形になって逆行、護衛に切られた。結果的に一名死亡、二名重傷。後、イギリス側は、幕府に謝罪文と賠償金10万ポンド、薩摩に下手人の死刑と賠償金2万5千ポンドを要求した。幕府は老中格・外国御用取扱役、小笠原長行が独断で支払い(文久三年五月)、謝罪文を出したが、薩摩藩は拒否した。最終的に薩英戦争に結び付く。
生麦事件起きる。薩摩藩国父・島津久光の行列に、騎乗のイギリス人四人が乗り入れる形になって逆行、護衛に切られた。結果的に一名死亡、二名重傷。後、イギリス側は、幕府に謝罪文と賠償金10万ポンド、薩摩に下手人の死刑と賠償金2万5千ポンドを要求した。幕府は老中格・外国御用取扱役、小笠原長行が独断で支払い(文久三年五月)、謝罪文を出したが、薩摩藩は拒否した。最終的に薩英戦争に結び付く。
▼管見3
生麦事件を攘夷事件とする考え方もあるが、私は事故だと思っている。薩摩藩兵は外国人との衝突を求めて京都に向かったのではない。
自分たちの目的のために進軍していたところへ、主君の隊列に馬で割り込んだ「敵対者」がいたので、彼らを排除しようとしたに過ぎない。
攘夷というのは、東禅寺事件のように、外国人(あるいは関係者)のいる場所へ殺傷を目的に意図的に向かう(待ち伏せも該当する)ものであると考える。『神戸開港三十年史』に「開国」という文字を揮毫した伊藤博文も若いとき、英国公使館を焼き討ちしたというが、これは攘夷だと定義する。
▲たたむ
- ◇岡山藩、国事周旋方発足。中央政局と積極的なかかわりをもつようになる。(『岡山県の歴史』頁259)
文久三年(1863)
 下関戦争。五月、長州藩、下関海峡を通過するアメリカ商船を砲撃。これに続いて、フランス艦、オランダ艦を砲撃する。六月、アメリカ艦・フランス艦から砲撃され、長州藩敗北。
下関戦争。五月、長州藩、下関海峡を通過するアメリカ商船を砲撃。これに続いて、フランス艦、オランダ艦を砲撃する。六月、アメリカ艦・フランス艦から砲撃され、長州藩敗北。 薩英戦争。イギリス代理公使ニールが乗船した軍艦7隻が鹿児島湾沖に投錨。その後、交渉の決裂により、砲撃戦に発展、最終的に薩摩藩がイギリスの要求を受け入れ和睦。薩摩藩は幕府から借金をして賠償金を支払ったが、犯人の処罰・借金の返済はうやむやにした。
薩英戦争。イギリス代理公使ニールが乗船した軍艦7隻が鹿児島湾沖に投錨。その後、交渉の決裂により、砲撃戦に発展、最終的に薩摩藩がイギリスの要求を受け入れ和睦。薩摩藩は幕府から借金をして賠償金を支払ったが、犯人の処罰・借金の返済はうやむやにした。
一般的に薩摩の敗北とされることが多いが、イギリス艦隊はこの時回答を得ることなく引き上げており(弾薬・燃料・食料等が不足したためと言われる)、また死傷者数はイギリス側が多い。薩摩藩内では戦勝気分に沸いたが、藩首脳は兵器の差などから和睦を選んだとされる。
イギリス側:(死者)旗艦ユーラシア艦長以下13名、(負傷者)50名。
薩摩藩側:(死者)5名、(負傷者)13名。
(ここの記述は、『幕末維新年表』に加えて、『幕末の蒸気船物語』頁57―72を参照した。)
▼管見4
薩摩が簡単に圧力に屈すると思っていたイギリス側は、その強さに驚いたのではないか、と思う。その後、薩摩とイギリスの関係が深まるのは、薩摩が西洋の武器の強力なのを知ったこともあるが、この戦いによる薩摩の能力をイギリス側が評価したこともあると思う。
▲たたむ
- ◇岡山藩、池田慶政隠居。茂政襲封。茂政は水戸藩・徳川斉昭の九男九郎丸。婿養子として迎えた。この後、岡山藩は尊王翼覇(尊王攘夷とともに幕府を補翼する)立場を明確にする。家中では牧野権六郎など尊攘意識を持つ中下層の家臣と守旧的な中層以上の家臣のあいだで藩論が二分された(『岡山藩』頁274―282、をもとにまとめた。)。しかし、次第に藩主主導の尊王翼覇が主流になっていく。
尊王翼覇という政策が内包する矛盾は、後に茂政の兄慶喜が徳川幕府第十五代将軍となることによりひずみが大きくなり、茂政の隠居へと繋がったと思う。
- ◇岡山藩、塩飽諸島・備中警備を命ぜられる。また、領内六か所に砲台建設を計画。(『岡山県の歴史』頁256―257)
元治元年(1864)
 幕府、イギリス・フランス・アメリカ・オランダとのパリ協定破棄。
幕府、イギリス・フランス・アメリカ・オランダとのパリ協定破棄。- ※プロイセン=オーストリア戦争。
 イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国艦隊下関を砲撃(下関戦争)。
イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国艦隊下関を砲撃(下関戦争)。- 〇禁門の変起きる。
- ◎第一次長州征伐。
- ◇岡山藩、長州征伐へ消極的出兵。直島警備に配置替え。(『岡山県の歴史』頁256)
- ◇岡山藩、新流大砲隊結成。(『岡山県史第九巻』頁67)(※1)
元治二年(1865)
慶応元年(1865)
- ※アメリカ南北戦争終結。不要になった銃器が大量に日本に流れ込むことになった。
 イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四ヵ国軍艦、条約勅許・兵庫開港要求のために兵庫に来る。
イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四ヵ国軍艦、条約勅許・兵庫開港要求のために兵庫に来る。
この結果、翌慶応二年、兵庫開港延期のために関税の変更(実質引き下げ)を盛り込んだ江戸協約が結ばれた。 安政の五ヵ国条約を朝廷が勅許。ただし、兵庫開港は不許可。
安政の五ヵ国条約を朝廷が勅許。ただし、兵庫開港は不許可。- ◇池田伊勢、天城池田家を相続。(『御奉公之品書上 池田貞彦』三。天城池田家は岡山藩家老家。三万石。池田伊勢はこの時13歳、後、西宮警衛隊総督。)
補注
※1.岡山藩、新流大砲隊結成。
「一八六四年(元治元)八月に安東四郎太夫(物頭、八〇〇石)を大砲隊長とする新流大砲隊の一番手が(中略)、翌九月に水野助三郎(物頭、一〇〇〇石)を大砲隊長とする二番手が結成され(以下略)」(『岡山県史』第九巻頁67)
「元治元年には家老池田兵庫を「文武惣督」に、物頭級および若年の平士を「文武惣引受加わり」「文武世話役」にそれぞれ任命し(中略)かくして同年九月いよいよ平士の子弟および士鉄砲を主体として、家中武士の新流(古流をも含む)大砲隊が結成され、翌慶応元年二月から調練が開始された。」(『岡山藩』頁258―259)。後者の記述の読み方によっては元治二年ともとれるが、『岡山県史』などを参考に元治元年だとした。

 (2019/12/12確認)
(2019/12/12確認)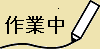

 (2019/12/12確認)
(2019/12/12確認)