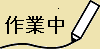慶応四年神戸事件を考える
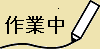
Ⅰ.争乱の時代
2.慶応二年から神戸開港前まで
慶応二年(1866)七月に将軍・家茂が死去、第二次長州征伐が中止された。その後、曲折を経て、同年十二月に徳川慶喜が将軍職に就いた。
その直後、十二月に孝明天皇が亡くなった。翌慶応三年一月に明治天皇(祐宮)が践祚され、外祖父中山忠能及び尊攘派の公家が謹慎処分を解かれた。
慶応三年二つの陣営の体制が変わったことにより、政治情勢の節目が変わった。対立はより激しくなり、駆け引きが続いた。
慶応二年(1866)
- ※普墺戦争始
- ◎第二次長州征伐。
- 【補足】長州藩兵が浜田へ進行したとき、浜田藩兵は松江城へ退却し、最終的に美作の飛び地へ逃れ、鶴田藩となった。(『新編 物語藩史』第九巻、頁280―281)また、小倉口で孤軍となった小倉藩は自ら城を焼き、香春まで退却、慶応3年1月まで抗戦。同年3月から香春に藩庁を移した。(『九州の諸藩』、頁76―80)
- 幕末の闘争は、局地的には既に内戦状態を呈していた。
- ◎将軍家茂、大坂城で没。享年二十一歳。公武合体で皇女和宮を正室とした将軍の若き死である。政略結婚の典型であるが夫婦仲は良かった由。
- ◎徳川慶喜、第十五代将軍に就任。三十歳。
- 〇孝明天皇崩御。享年三十六歳。
孝明天皇の死について
孝明天皇は、攘夷思想が強く、幕府の外交に大きな影響を与えた。いっぽう、政治向きには幕府を信頼していて、攘夷派の公家には都合が悪い存在だった。このあと幼帝(数え年十六歳)を迎えることとなり、策謀派は動きやすくなった。新天皇即位に際して、多くの討幕派公家が復権した。真偽は定かではないが毒殺説もある(『幕末維新史年表』頁178他)。
- ◇倉敷浅尾騒動起きる。事件は長州藩第二奇兵隊が倉敷代官所・総社浅尾藩陣屋を襲撃した事件であり、岡山藩にとっては領外で起きたことだが、援軍を求められたあとの対応を責められ、責任者を罰した。(『岡山県の歴史』頁263―265) ◇岡山藩、農兵隊取り立て始まる。(同前、頁268)
慶応三年(1867)
▼管見1
徳川慶喜は安政の大獄という逆境も経験した三十歳の政治家であるが、立太子を経ずして天皇に即位した十六歳の明治天皇にどの程度の政治力があったかは疑問がある。明治初頭の「朝廷の裁断」を考えるとき、このことを視野に入れておく必要がある。
個人的には明治天皇というと権威ある偉丈夫というイメージがあるが、それは維新の元勲が亡くなり、かつ天皇自身も経験を積まれたころからのものであろう。
▲たたむ
 十二ヶ条規定書により、居留地を神戸にすることを決める。:イギリス・アメリカ・フランス・オランダ公使とのあいだで兵庫開港による居留地を生田川と宇治川の間(神戸市中央区)と定めた(『神戸市史 本編総説』、頁65。原文解読文は『兵庫県史 史料編 幕末維新』1、頁463―464)。
十二ヶ条規定書により、居留地を神戸にすることを決める。:イギリス・アメリカ・フランス・オランダ公使とのあいだで兵庫開港による居留地を生田川と宇治川の間(神戸市中央区)と定めた(『神戸市史 本編総説』、頁65。原文解読文は『兵庫県史 史料編 幕末維新』1、頁463―464)。- ◎柴田剛中、外国奉行兼帯大坂町奉行を拝命。
 兵庫開港、勅許。(三月五日、将軍徳川慶喜、兵庫開港を願い出る。五月二十四日勅許。)
兵庫開港、勅許。(三月五日、将軍徳川慶喜、兵庫開港を願い出る。五月二十四日勅許。)
▼管見2
実に涙ぐましいまでの幕府の努力である。開港準備も含めて、基礎固めの大方が幕府によったといえる。
我々昭和世代が見た時代劇映画では、幕府は閉鎖的、朝廷派は開明的であったように記憶する。そうではなかったに思える。
『神戸開港三十年史』などいくつかの神戸地域の資料を見ると
▲たたむ
ここから開港準備始まる
- 七月九日
- ◎柴田剛中、大坂町奉行兼帯で兵庫奉行を拝命。
- (神戸開港期の柴田剛中に関することは、「神戸開港に臨んだ外国奉行柴田剛中―大坂町奉行・兵庫奉行兼帯期の動向―」『徳川社会と日本の近代化』、頁681―704、及び『日載』十による。『日載』を「柴田の日誌」と書くこともある。)
- ―このあと十二月七日の開港へ向けて、柴田剛中の指揮のもと、補佐として森山多吉郎などが活動し、各種の作業が本格的に進められた。枝番としてアルファベットを付す。―
- 七月二十三日
- ◎西国往還の付替を大坂代官斎藤六蔵に命じる。(『神戸の歴史 研究編』頁236)
-
- 八月五日
- ◎a.海岸波除地、荷揚場石垣入札。
- ※九月下旬ごろ神戸居留地会所が設置され、柴田の日誌に「会所出勤」という言葉がみられる。これ以降、開港日まで、精力的に見回りや外国外交官と折衝などを続ける。
-
- 九月十六日
- ◇岡山藩家老・日置帯刀、近藤勇と会う。帯刀は神戸で衝突した隊の隊長。
- 帯刀自身は勤皇であったとされる。この年の七月から京都に滞在し、広島藩家老・石井修理など各藩の家老と交流し、各藩の藩主とも面会している。この遭遇は佐賀藩主・松平肥前守(鍋島直正)を尋ねた時のことと思われる。九月十六日に京都出立。(『御奉公之品書上 日置英彦』八、同日)
-
- 九月二十六日
- ◎b.大坂島屋が運上所建設落札。
-
- 十月四日
- ◎c.貸倉庫3棟、運上所1棟建設を島屋が落札。
-
- 十月十四日
- ◎d.石井村庄屋谷勘兵衛、西国街道付替道工事の請書を提出。ただし、事前に杭打ちなどは進められていた。(『神戸の歴史 研究編』頁237)
- 〇大政奉還勅許
- 大政奉還の「勅許の沙汰」の内容を『徳川実記』で見てみる。
▽資料・徳川実記
【読み下し文(一部抜粋)】
御所より仰せ出されそうろう、御書付写し
祖宗以来、御委任厚く御依頼在りなされ候えども、方今、宇内の形勢を考へ察し、建白の旨趣、尤に思召され候間、聞食(きこしおさ=治める)れ候、尚天下と共に同心尽力を致し、皇国を維持、宸襟安んじ奉るべく、御沙汰候事
御所より仰せ出されそうろう、御書付写し
大事件・外夷一條は衆議(を)尽くし、其外諸大名伺い、仰出られ等は、朝廷両役に於いて取扱(い)、自余の儀は、召(の)諸侯上京の上、御決定之あるべし。
夫迄之処、(徳川)支配地、市中取締等は、先(ま)ず、是迄の通にて、追て御沙汰に及ぶべく候事。
『続徳川実記』第五編(頁一四四四―一四四五)
読みやすくするために、原文を読み下し、句読点、送り仮名などを追記した。一部句点を読点にするなど変更し、また、一部意味を補記した。朝廷両役は『復古記』巻一、慶応三年十月十五日、第一冊(頁十―十一)によれば「議奏」「傅奏」である。
▲たたむ
- 「衆議を尽くす」ことや「諸大名と朝廷の間は朝廷側の役職者(議奏・傅奏)を通すこと」そして「追って沙汰するまで」の制限付きではあったが、外交及び徳川旧領の管理はこれまで通りとされている。行政機構の権限と責任は徳川幕府に残った。
この頃兵庫近辺に「ええじゃないか」騒動が続く
兵庫津では十一月十五日ごろから、お祓のほかに諸神仏・経文・金銭が降った。(中略)市中に老幼男女が「ええじゃないか」のはやしで踊り、町々から屋台や曳物がでて豪華を競った。(後略)(『兵庫県史』第5巻、頁544―547。)
- 十一月十八日
 柴田剛中がミットフォード(1868年1月1日にイギリス公使館二等書記官)・サトウ(同日本語書記官)と打ち合わせ。(『一外交官の見た明治維新』下、頁85。「神戸開港に臨んだ外国奉行柴田剛中」頁691の次「表1」。『日載十』)
柴田剛中がミットフォード(1868年1月1日にイギリス公使館二等書記官)・サトウ(同日本語書記官)と打ち合わせ。(『一外交官の見た明治維新』下、頁85。「神戸開港に臨んだ外国奉行柴田剛中」頁691の次「表1」。『日載十』)-
- 十一月十九日
- ◎e.運上所棟上げ。
-
- 十一月二十九日
- 〇長州藩兵、摂津の打出浜(兵庫県芦屋市)に上陸
- 上記は『幕末維新年表』頁190。『戊辰戦争』では十一月二十八日(頁18)である。
- なお十二月一日になって、長州藩兵の一部が、西宮駐屯。本部を六湛寺に置く(同前)。ここには、神戸での衝突後、岡山藩西宮警衛隊総督・池田伊勢が宿営した(同人奉公書)。
討幕派の兵力上京
広島藩・薩摩藩・長州など西国の討幕派の藩が海路、陸路を東上して来る。西宮周辺、大坂湾などに停泊したり、上陸し、待機していた。また、これに続いて、陸路を東上する部隊も十二月に西国街道を進んだ。この当時の在京勢力は、広島藩750人、薩摩2,800人、長州1,600人とされる。
いっぽうこの時期、幕府も直属兵力を上坂させた。鳥羽伏見の戦いが始まるまでに、大坂城に集結した幕府方の勢力は15,000人という。(『兵庫県史』第5巻、頁534―537。『戊辰戦争』頁18―19)
移動手段として、蒸気船が多いのが目を引く。
十二月になって、各国公使が横浜から神戸に参集し、一月十一日の衝突の時、現場にいた外交官が揃っている。
米国弁理公使ファン・ファルケンバーグがスチュアート国務長官に送った文書を参照する。
▽資料・ファン・ファルケンバーグの報告
本官は、12月28日(十二月三日)に当地に到着しましたが、シェナンド号は前の寄港地の兵庫から11マイルしか離れていない河口に投錨しています。(中略)大英帝国の代表団は、英国国王の軍艦アドベンチャー号で、シェナンド号と同じ日に横浜を出港して当地に直行し、12月23日の夜に到着しております。
フランス公使は、ロプラス号で30日(十二月五日)頃に、イタリアとプロシアの代表は31日に到着します。現在兵庫にいるオランダの代表は当地に日帰りで来るだろうと見られています。(日付は西暦、( )の和暦は参照のために補記した。)
(『神戸地域学』頁23.原文は『神戸市史資料』三、巻末英文頁15、16,18。邦文資料のあとに英文資料があり、頁付けは逆順)
【補注】『遠い崖』6、頁92前後を参照する範囲では、英公使パークスは慶応三年十一月二十九日(1867年12月24日)に横浜から大坂に到着している。これらの齟齬は、各国公使の記録、自伝などで時々見られる。また、外国外交官の自伝などでは神戸開港当日の記述は他のことにくらべ扱いが軽い。
▲たたむ